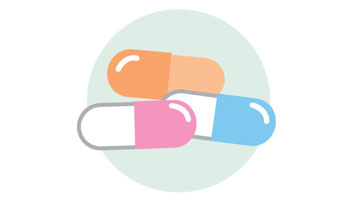治験
治験
参加募集中の治験▼
現在当院では、下記の治験に参加していただける方を募集しています。- 現在、参加募集中の治験はありません
- 腎性貧血と診断された方
- アルツハイマー病と診断された方
- 糖尿病性腎臓病と診断された方
治験について
1.治験とは
ひとつのくすりが誕生するには、長い研究開発期間を必要とします。化学合成や、植物、土壌中の菌、海洋生物などから発見された物質の中から、試験管の中での実験や動物実験により、病気に効果があり、人に使用しても安全と予測されるものが「くすりの候補」として選ばれます。この「くすりの候補」の開発の最終段階では、健康な人や患者さんの協力によって、人での効果と安全性を調べることが必要です。 こうして得られた成績を国が審査して、病気の治療に必要で、かつ安全に使っていけると承認されたものが「くすり」となります。 「くすりの候補」を「くすり」として国から認めてもらうために、健康な方や患者さんのご協力のもとに行う臨床試験のことを「治験」と呼びます。~新しいくすりの誕生~
基礎研究(2~3年)試験管内で合成されたり、天然の物質から精製されたり、実験室で新しい「くすりの候補」が創りだされます。

非臨床試験(3~5年)動物などを使って「くすりの候補」の効き目と安全性を詳しく調べます。

治験(3~7年)
第Ⅰ相試験:
少数の健康な人を対象に、安全性と、治験薬が体の中にどのように吸収され体の外に出て行くかなどを調べます。 第Ⅱ相試験:
少数の患者さんを対象に、効果、安全性、使用方法などを調べます。
第Ⅱ相試験:
少数の患者さんを対象に、効果、安全性、使用方法などを調べます。 第Ⅲ相試験:
多数の患者さんを対象に、現在使われている薬などと比較して、効果と安全性を確認します。
第Ⅲ相試験:
多数の患者さんを対象に、現在使われている薬などと比較して、効果と安全性を確認します。
 第Ⅱ相試験:
少数の患者さんを対象に、効果、安全性、使用方法などを調べます。
第Ⅱ相試験:
少数の患者さんを対象に、効果、安全性、使用方法などを調べます。 第Ⅲ相試験:
多数の患者さんを対象に、現在使われている薬などと比較して、効果と安全性を確認します。
第Ⅲ相試験:
多数の患者さんを対象に、現在使われている薬などと比較して、効果と安全性を確認します。
厚生労働省への承認申請と専門家による審査(2~3年)
厳正な審査をパスし、承認されることによってはじめて「くすりの候補」が「くすり」となります。

新しいくすりの誕生

製造販売後調査
第Ⅳ相試験:
市販された薬を使用し、効果や安全性についてさらに評価・分析を行います。
2.インフォームド・コンセント
医師は「くすりの候補」を使えば病気に効果があると期待される患者さんに、治験への参加をお尋ねします。患者さんの自由な意思にもとづく文書での同意があってからでないと治験は始められません。 この「説明と同意」のことを「インフォームド・コンセント」といいます。インフォームド・コンセントの手続き
医師またはCRC(治験コーディネーター)から治験の目的、方法、治験に参加しない場合の治療法、「くすりの候補」の特徴などが書かれた「説明文書」を手渡され、その内容が詳しく説明されます。患者さんは、それに対しわからないこと、確認したいことなど、納得するまでどんなことでも質問することができます。
そして、治験に参加するかしないかは、誰からも強制されることなく、自分の意思で決めてください。説明を受けたその場で決めず、説明文書を持ち帰ってご家族に相談してから決めることもできます。
参加することに同意いただきましたら、「同意文書」に患者さんと治験を担当する医師が自筆で署名します。同意文書の控えと説明文書は患者さんに渡されます。
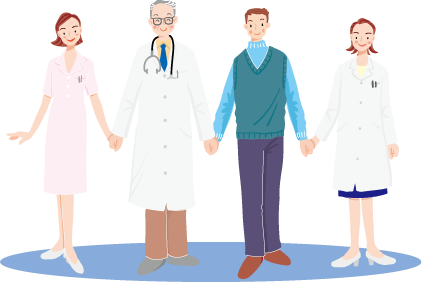
3.治験審査委員会(IRB)とは
「治験の計画」が治験に参加される方の人権や安全の保護および科学的に適切であるか審査する独立の委員会を治験審査委員会とよびます。治験の依頼を受けた病院が治験を開始するためには、この治験審査委員会の承認と院長の了承を得てからでなければなりません。
治験に参加される方の人権と安全性を保護する見地から、治験審査委員会には、治験の依頼を受けた病院とは利害関係のない人や医学、薬学などの専門家以外の人も委員として加わります。また、この委員会は、治験がルールに沿って行われているか、「くすりの候補」に関する新たな副作用の情報があった場合には、治験を継続してよいかについても審査します。
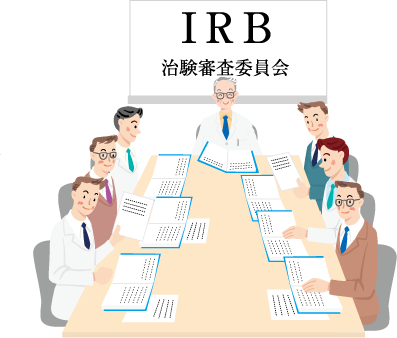
4.治験コーディネーター(CRC)とは
治験コーディネータ―(CRC〈シー・アール・シー〉:Clinical Research Coordinator)は、治験の実施全般にわたってサポートする専門スタッフです。
治験に参加される患者さんの相談窓口として、通院(又は入院)スケジュールの調整、服薬状況の確認や、治験(臨床試験)に携わるチーム内の調整もしています。治験に関する質問はご遠慮なく、CRCにお尋ねください。
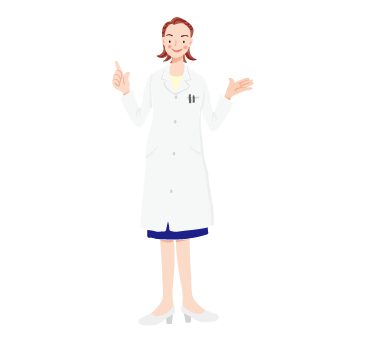
5.治験のQ&A
Q1)だれでも治験に参加できますか?
A1)治験ごとに参加できる基本的な条件が定められています。その条件を満たす方に、診察や検査を受けていただき、患者さんの安全の確保と、治験の目的に合致していることの最終的な確認をおこなったうえで、参加が決定されます。Q2)治験に参加すると、費用がかかりますか?
A2)治験薬を使用している期間中の検査費用と、一部のくすりの費用は無料となる場合がありますが、初診料やその後の診察費などについては通常の診療と同様に患者さんの負担が発生します。治験薬は通常、製薬会社が無料で提供します。そのほか通院の交通費などの負担軽減費を、一定の範囲でお支払いしています。参加する治験によっても条件がことなりますので、参加の依頼があったときなどにお尋ねください。Q3)治験に参加すると、どんなメリットがありますか?
A3)治験への参加の基本は、患者さんの善意に基づくボランティアです。将来病気で苦しむ患者さんの治療に役立つ「新しいくすり」を誕生させるという社会貢献ができます。また、治験中は通常の治療よりも専門医による詳細な診察や検査と、病状の経過と検査結果についてのくわしい説明を受けることができますし、治験薬(おくすりの候補)が、従来のくすりよりも患者さんに良く合うこともあります。治験の場合は、検査代やお薬代がいつもの診療より安くなることがあります。Q4)デメリットとしては、どのようなことはありますか?
A4)治験中は体調に変化がないか慎重に診察するために、いつもより来院する回数や検査の頻度が多くなることがあります。くすりの飲み方や生活の仕方など、気を付けて守らなければならないことがあります。まれに、これまでに知られていなかったような副作用が出る可能性があります。これらのことは担当医師やCRC(治験コーディネーター)から説明がありますので、ご了解のうえで参加していただくことになります。Q5)治験への参加を取りやめることはできますか?
A5)はい。治験への参加は患者さんの自由意思ですので、いつでも担当医師に言って取りやめることができます。取りやめた場合にも、患者さんに不利益となる扱いを受けることはありません。不安なことがありましたら、担当医師やCRC(治験コーディネーター)などにお申し出ください。Q6)プライバシーは守られますか?
A6)患者さんの個人情報の保護については、法律で守秘義務が課せられ、違反すると罰せられます。治験に参加したこと自体も関係者以外には知らされず、治験中の個人情報も厳密に管理され、治験の結果は認可を得るための資料などに利用されますが、個人の情報が公表されることはありません。製薬会社や厚生労働省により、カルテや検査データなどが正しいかどうかを確認することがありますが、その場合でも氏名や住所などの個人情報は公開されません。いかなる場合も、個人を特定できることはなく、プライバシーは守られます。Q7)治験中に、守るべきことはありますか?
A7)安全の確保と信頼できるデータを得るために、患者さんには治験薬の服用の時間や回数、検査のための通院日、服用の記録をつけるなど、守っていただかなければならないことがいくつかあります。これらは、担当医師やCRC(治験コーディネーター)から具体的に説明があります。Q8)治験ってお薬のテストだけなのですか?
A8)世の中でまだ公的な認可を受けていないものをテストするのが治験です。その意味で、開発中のお薬の治験を行うことが圧倒的に多いのですが、実はお薬以外でも治験があります。それは「医療用機器」とよばれる装置、器具や細胞製品などについての治験で、例えば新しい手術用具や、レーザーを使った治療器具など、「安全性」と「有効性」を確認するという意味ではお薬と同様の治験が行われます。Q9)治験に参加したいけどどうすればいいの?
A9)病院内に掲示されている治験参加のポスターや病院のホームページを見て治験参加を希望されましたら、患者さんから、担当医師または治験事務局に治験の参加についてご相談ください。当院の治験実績
治験および製造販売後臨床試験の受託実績を疾患領域別にご紹介します。消化器内科領域
逆流性食道炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、過敏性腸症候群呼吸器内科領域
気管支喘息、COPD内分泌代謝科領域
2型糖尿病、耐糖能異常、糖尿病性神経障害循環器内科領域
慢性心不全、高脂血症、肥満症肝臓領域
肝硬変腎臓領域
糖尿病性腎臓病、腎性貧血ペイン領域
慢性腰痛、帯状疱疹後神経痛整形外科領域
骨粗鬆症婦人科領域
子宮内膜症癌領域
癌化学療法に伴う悪心・嘔吐神経内科領域
アルツハイマー病臨床研究
1.臨床研究について
当院では、薬物の有効性に関するもの以外に、人を対象とした臨床研究を実施しています。臨床研究とは、 医療における疾病の予防方法、診断方法及び治療方法の改善、疾病原因及び病態の理解並びに患者の 生活の質の向上を目的として実施される医学系研究のことをいいます。 診療情報を臨床研究に利用させていただく場合、臨床研究倫理審査委員会の審議を経て行われます。 研究への協力を希望されない場合は、総務企画課までお知らせください。 研究不参加を申し出られた場合でも、何ら不利益を受けることはありません。2.研究事例
令和7年度| 審査日 | 承認番号 | 所属 | 責任者 | 研究名 | お知らせ |
| R7.6.3 | 2025-001 | 婦人科医師 | 池田 俊一 | 子宮頸部のハイリスクHPV持続感染に対する液体窒素療法の効果 | |
| R7.6.3 | 2025-002 | 脳神経内科医師 | 沓名 章仁 | JCHO東京高輪病院職員における頭痛の実態 | |
| R7.7.9 | 2025-003 | 脳神経内科医師 | 沓名 章仁 | 脳卒中登録研究 | |
| R7.7.9 | 2025-004 | 3東看護師 | 吉永 想 | 転倒リスクの高い患者の傾向の分析と予防対策 | |
| R7.7.9 | 2025-005 | 3西看護師 | 水野 和生 | チェックリストを用いた身体抑制の一時中断のためのカンファレンス充実に関する研究 | |
| R7.7.9 | 2025-006 | 4階看護師 | 永山 桃 | 整形外科における認知機能低下がみられる患者に対する転倒予防の看護実践の実態 | |
| R7.7.9 | 2025-007 | 5階看護師 | 小山 香代子 | 当院病棟看護師の栄養管理に対する意識と知識の実態調査 | |
| R7.7.9 | 2025-008 | HCU看護師 | 肥後 果梨 | カテーテル治療に従事するHCU看護師のシミュレーション実施前後における知識の獲得とストレスへの関わりについて | |
| R7.7.9 | 2025-009 | 外来看護師 | 石綿 由貴枝 渡邉 帆南 | 日中受付時間外来院患者を対象とした電話トリアージフローの開発と効果検証、アンケート調査 | |
| R7.7.9 | 2025-010 | 言語聴覚士 | 竹内 明香 | 言語聴覚士の呼吸ケアへの関与に対する他職種の認識の調査 | |
| R7.7.9 | 2025-011 | JCHO東京山手メディカルセンター老年内科診療部長 | 眞喜志 直子 | 治療可能な認知症の非専門医における認知度の調査 |
| 審査日 | 承認番号 | 所属 | 責任者 | 研究名 | お知らせ |
| R6.5.31 | 2024-101 | 歯科口腔外科 | 良知 麻衣子 | 疫学調査「口腔がん登録」(信州大学 歯科口腔外科教室 症例登録) | |
| R6.7.2 | 2024-001 | 看護部 | 橋本 美弥 | アナムネ用紙変更に伴う病棟看護師・訪問看護師の継続看護に対する情報収集の違いと変化の検証 | |
| R6.7.2 | 2024-002 | 看護部 | 竹澤 英子/利根川 弘美 | 同意書確認のリーフレット導入によるサインインまでの時間と看護業務の変化 | |
| R6.7.2 | 2024-003 | 看護部 | 山下 真由美 | 認知症マフの導入が認知症患者の安全と安楽に与える影響 | |
| R6.7.2 | 2024-004 | 看護部 | 加藤 菜月 | 退院支援情報収集シートの導入による病棟看護師の意識変化~下肢の骨折の患者に着目して~ | |
| R6.7.2 | 2024-005 | 看護部 | 小田 麻衣子 | リーフレットの運用とカンファレンスの充実化による体幹抑制の減少率 | |
| R6.11.11 | 2024-102 | 消化器内科 | 岸本 有為 | 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築((一社)日本消化器内視鏡学会 症例登録) | |
| R6.11.15 | 2024-006 | 整形外科 | 岡田 智彰 | 鏡視下肩腱板修復術の経過と骨密度の関係の検討 | |
| R6.12.27 | 2024-103 | 呼吸器内科 | 鎌田 啓佑 | 菌血症に関する抗菌薬早期効果判定モデル作成と多角的解析研究:多施設共同後ろ向きコホート研究(研究者の変更等に伴う更新申請) | |
| R7.03.14 | 2024-104 | 消化器内科 | 岸本 有為 | 分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)の前向き追跡調査(他施設共同研究)結果のサブグループ解析によるIPMN由来癌・IPMN併存通常型膵癌発生リスク因子探索(九州大学大学院医学研究 臨床・腫瘍外科学分野 症例登録) |
| 審査日 | 承認番号 | 所属 | 責任者 | 研究名 | お知らせ |
| R5.4.20 | 2023-001 | 耳鼻咽喉科 | 井上 彰子 | 東京高輪病院耳鼻咽喉科における外耳道真菌症の原因真菌や背景因子に関する後方視的研究 | |
| R5.4.20 | 2023-002 | リハビリテーション科 | 浪越 啓史 | 複合高周波電気刺激による長・短腓骨筋の質的変化およびパフォーマンステストへの影響 | |
| R5.4.20 | 2023-003 | リハビリテーション科 | 山上 夏乃 | 当院における肩関節周囲炎の可動域等の推移について | |
| R5.4.20 | 2023-004 | リハビリテーション科 | 木村 亮太 | 複合高周波電気刺激が抗重力筋に及ぼす影響について | |
| R5.5.15 | 2023-005 | 外科 | 山本 順司 | 後天的な性染色体喪失と暦年齢の関係に関する研究 | |
| R5.8.10 | 2023-006 | 看護部 | 渡邉 淳子 | 地域包括ケア2病棟合同での患者レクリエーションプログラム実施における業務調整への取り組み | |
| R5.8.10 | 2023-007 | 看護部 | 東田 栄 | 心不全カンファレンスの内容を外来看護師間で情報共有する「情報共有シート」の効果 ~心不全患者の継続看護を目指して~ | |
| R5.8.10 | 2023-008 | 看護部 | 田端 美香 | 新人看護師指導に関わる上で先輩看護師が大切にしていること | |
| R5.8.10 | 2023-009 | 看護部 | 脇野 友里恵 渡邉 帆南 | 病棟看護師における身体抑制具に対する理解度の実態調査 | |
| R5.11.27 | 2023-011 | リハビリテーション科 | 浪越 啓史 | 退院後の生活空間の経時的変化と関連する要因~転倒を起因として入院した高齢者を対象とした記述研究~ |
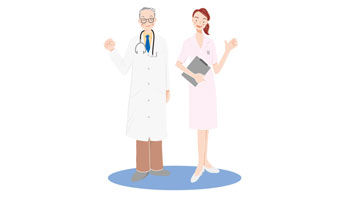 治験について
治験について